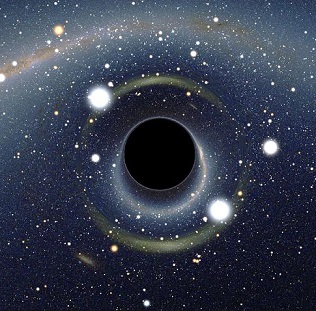長文の連投、失礼致します。
来週『男の母性』を取り扱う前に、反対側からの誠意を採り上げることで行う”地鎮”となります。
木曜記事はあっさりと仕上げます。
では記事へ。
《虚無の依り代》
意識の中立を保ちゼロの見地から歌い上げることの出来る者へ、制作者達が楽曲を提供する時、それは「与える」のではなく「捧げる」ものとなっている。

勿論全部が全部とは言わないが、1980年代から90年初頭までこの端末に捧げられた作品には、2018現在でも驚く程遜色なく、意識へと深く響くものが幾つもある。
この深さはどこから来るのか。
観察していて、ふと気づいた。

数あるアイドルの中で、歌うことを通して虚無に向き合った者って居ただろうか?
アイドルは、華やかさに満ちて希望を歌う。
ふわふわした夢の世界を歌う。
青春の甘さやほろ苦さを歌う。
時に初々しく、時に魅惑的で、何にせよ別次元。
そんな存在である。
別次元は別次元なのだが、虚無は全然甘くもほろ苦くもないし、希望に満ちてもいない。
「これこれ、この味!」と安心させてくれるお約束がない。
その虚無に中森明菜と言う端末は歌の中で対峙し、聴く者に感覚を伝えている。
確かに最初は「スローモーション」など、甘い恋の予感なんか歌っていたのだが、あっという間に成長しメキメキと変化した。
ヒヨコの時は小さく可愛く他とも似ていたのに、育ったらニワトリじゃなく火の鳥だった感じ。
周囲も世間も、さぞビックリしたろう。
群を抜く独自性がありながら、「特別じゃない どこにもいるわ」とも歌える。
凡を堂々と言祝ぐ、その器の大きさ。
芥川が眇めて「唯ぼんやりした不安」として捉えた虚無。
それを、明菜の意識はガン見する。決して目を逸らさない。
文豪じゃなくアイドルがである。

「凄っ!」
と、仰け反った。
歌やナリで得体の知れない不穏さを演出し、凄味を出そうとする者は大勢居る。
だが、演出せずとも内から自然と出る凄味には到底及ばない。
どれ程世間から離れようが、世間は決してこの端末を、成したその仕事を忘れないのはその為だ。

本人が全く望まなくとも結果最も得体が知れないし、不穏さも滲み出ている。
その“不穏”は、不覚のエゴ達が穏やかで居られずにざわつくことで起きる。
明菜の歌はエゴを追い立てる。
のうのうと惰眠を貪らせない、真っ向から突きつける通告がある。
第一声が「愚図ね」で始まるこの歌も「全ての男(分割意識)よ、モーゼたれ」と言う、力強い発破である。
意識がグズグズと「坊や」状態に留まりがちな方は、一度正座して聴いてみられることをお勧めする。
淋しさや激情を歌った端末は他にも居るが、いずれも女の情念に絡めとられ、エゴを酔わせる予定調和の域を出ていない。
アイドルと言う立ち位置で虚無感を歌いきった存在は、宮司の知る限り、この端末の他には無い。

1990前後では、全てが虚空から発生していることなど世間は知る由もなく、虚空は虚無として扱われた。
虚無感は払拭すべきもの、虚無は避けるべきものだった。
そうした中でも、全母である虚空からの呼びかけは常に起きていた。
全母の求めに応じ、歌を通したコンタクトを引き受けた、その愛と勇気には只々敬服する。
不覚のまま虚無の依り代としての役割をこなすことは、大変な力を要し消耗が半端ない。

仕事を含め生活は度々変調をきたし、時には「難破船」化することもある。
それ程の危ない橋。
だが、彼女は引き受けた。
中森明菜とは、虚無の奥にある“何か”を見つめ、万人に知らしめようとした孤高の巫女である。
その生き様に、男気を感じる。

女としての歌も、引き受けて完全にやりきると、それは男気と化すのだ。
変容の時代が既に来たことを理解されているグッドセンスな皆様は、この様に積み重ねられて来た「その時代にはこうとしか成し得なかった男気仕事」に深く感謝し、変容の礎として頂くこと。
そしてご自身の燃え上がる愛と共に、軽やかに新時代の男気を発揮されること。
愛と愚図とが相容れない事実は、実践でのみ知れることだ。

無を歌う、男気の女神。
(2018/1/15)