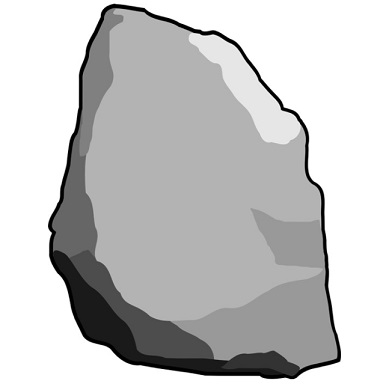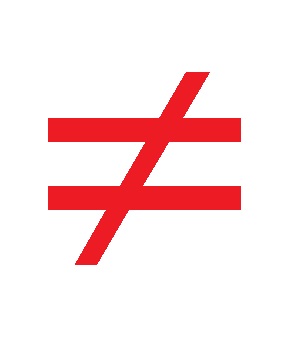《母通し》
愛は常に新しい、と前回記事に書いた。
新しさを感じるには、愛の元となる無限の天意が放たれる、全母たる虚空に通じることが、何においてもまず必要となる。
だから、内なる全母性を開くことを申し上げ続けて来た。
一瞬の垣間見程度だと「あの時のあの感覚」「あの時の温かさ」「あの時の明晰さ」と、“あの時縛り”で固定化され、素敵な思い出や「きっと又いつかは感じられるはず」と言う心のお守りみたいなものに留まる。
通じると、流れ来るものが止まない。

絶えず流れる“これ”は何だ、何故尽きないのだと、天意からの愛について意識がその無限性を少しずつ腑に落とし、やがて「そうだ、当たり前のことだったのだ」と認め始める。
当たり前、そしてこの当たり前がどれ程素晴らしいかを分かり始める。
通じる過程でエゴの大好きな枯渇ゲームや恐怖ゲームは溶けて流れて消えて行ってしまうので、そうしたゲームへの未練が残っていると「ちょっと、待った!」とばかりに手離すのが惜しいものを引っ掴んで、流れを塞ぐ。
これが「覚めそで覚めない」葛藤ゲーム。
だが、全体一つの流れが加速し続けるこの時代には、もうゲームとしてのバランスを保つことは難しい。
通路ごと「わあー!」と押し流されて行ってしまう。

最後のオイシイ所として取っておいたウォータースライダーイベントなら、それはそれで結構なのかも知れないが、サクナダリには水から上って来て「さぁもっかい!」となる為のスロープもないし、階段も手すりも、蜘蛛の糸もない。
覚めるのも、覚めぬのも、覚悟の有る無し抜きにして、どちらも金輪際に変わりない。
金輪際を意志して覚める者は、変容の時代に新しき愛の存在として降り立ち、輝き始める。
全母の天意を受け取り、生ける空間としてその通り道になり、愛として放つ。

そうする中で自然と、通り道である愛の発揮者にも天意からの愛が満ち、活き活きとする。
全なる母は形を持たない。
天の国とか地の果てとか、どこか遠く離れた場所に居る“特別優れたお母さん”をイメージし、そこに向かってお強請りしても息が切れ、声が枯れるばかり。
かつて不覚行動を体験し味わうことがテーマだった時代には、聖母や救い主と言った特定のイメージに憧れたり縋ったり祈ったり願ったりすることも「やってみようね」の一覧に載っていたので、全母たる虚空からの応援があった。しかし、
聖母≠全母
化身だとか、そう言うことも一切ない。
とっくに申し上げたことではあるが、人類には時代の潮目が変わってもまだ特別な代表者にすぐ期待をかけて縋ろうとし、又、こうありたい理想とする癖が染みついている。
なので、改めて書かせて頂いた。
聖母は常に遠い存在のままだが、全母に距離はない。母通せば、母遠しとはならない。必要のある母力は、全母力の方である。
「母」のイメージには聖母を始めとする色んな理想や美学や柵が引っ絡まって彩色が施されている。
それらを超えて感覚的に
「!」

となる、“Water‼”的瞬間が訪れるまでが、中々険しい。
井戸を掘るのに岩盤を砕いても水がまだ出ない状態に似ている。
そこからちょろちょろとでも水に触れる瞬間が生まれると、それを呼び水として次第に母力は増す。
覚める意志があったとしても、途中は「何だかマリアに似てる!」と気に入った石ころを発見すればつい飾りたくなって、それで水の出口を塞いでみたりと、行きつ戻りつがあるかも知れない。
それでも、掘り進めることを止めなければやがてそうした遊びにも入れない程、天意からの愛が溢れて来る。

水を止めているのは、「これはこうであるべき」と言う思い込みが様々なかたちになって広がったもの。
「自らこうあるべきと求めて来た自分像」
「こうあって欲しいと周囲に求められてきた自分像」
「こうあるべきと思っている理想の世界」
「人間や人生に関する何となくの限界設定」
「その限界を超えてこうなったら良いなとイメージする、実際はエゴの範疇を出ていない思い描き」
全母性の歓びが満ちていると、こうした「べき」「べし」が溶け出し、泡の様に浮かんでどれも通り過ぎて流れて行く。
「べき・べし」の制限がない爽やかな意識には。聖母も少女の様に映り、愛で観て慈しむのみとなるのだ。

聖母にも「お帰り」の時代。
(2021/1/7)