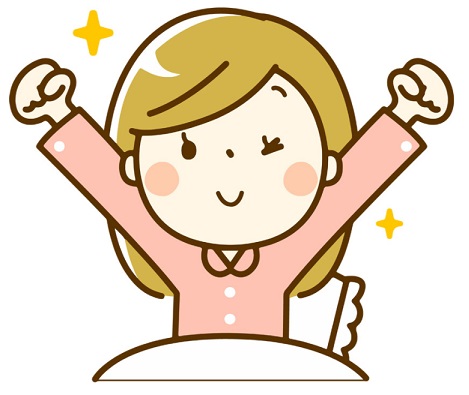《覚めゆく世界》
「春眠暁を覚えず」とは、春の夜は短く、過ごし易い気候であることから、つい寝過ごしもしてしまうという意味。

孟浩然の詩『春暁』を基にした表現である。
『春暁』には続きがあり
「春眠暁を覚えず、
処処啼鳥を聞く、
夜来風雨の音、
花落つること知る多少」
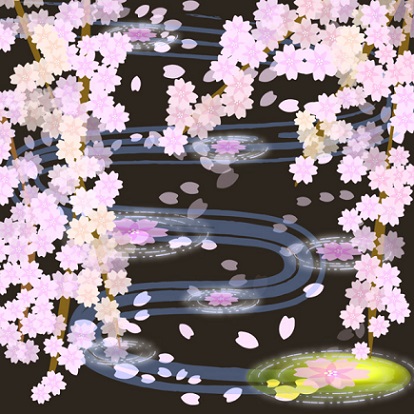
(春の眠りは心地よくて夜明けも知らず、
いつの間にか鳥のさえずりが聞こえる。
昨晩は嵐の吹く音がしたが、
おそらく花が沢山散ったことだろう)
となっている。
調べていたら、使用例に「春眠暁を覚えずで、何度起こしても息子が起きない」とあった。

「いやぁついつい寝過ごしました」の自己申告だけでなく、中々起きないお寝坊について、起こしたいと奮闘する人物が使ったりもするのだ。
こうした場合、当の寝坊助には心地よい眠りであっても、起こしたい者にとっては、貪られる惰眠であり、あまり良い感じとされていない。
御神体と分割意識が日々行う眠りは、新生に欠かせない重要なものである。
一日十分に味わった体験を虚空に還し、消化&昇華し、そして真新しい一日が始まる。
呼吸や点滅と同じに、起きて寝てにも、一つの生と死がある。
不覚状態を意識の眠りと例えたりすることもあるので混同しがちだが、必要な睡眠と不覚の無明は違うものである。
無明の不覚者でも、「春眠暁を覚えず」の表現を使ってお寝坊を指摘したりする。
眠りについて怠けとか、無駄とか、「よろしくないもの」の印象を持つことだって可能なのだ。
早起きしたからこそ見られる瞬間について綴った有名な例が『枕草子』の冒頭。

「春はあけぼの。
やうやうしろくなりゆく山ぎは、
すこしあかりて、
紫だちたる雲のほそくたなびきたる」
この後に「夏は夜」「秋は夕暮れ」「冬はつとめて」と続き、まとめると四季折々の清少納言的ベストタイミングについて書かれている。
ちなみに冬の「つとめて」とは早朝のことで、朝早くなら「あけぼの」と被る様だが、ちょっと違っている。
あけぼのは夜が明けて行く頃
つとめては夜が明けて間もない頃

時間帯で言えば「あけぼの」の方が早くなる。
どちらもほんのりとした暗さの残る中で次第に明るさが増して行く時に変わりない。
この様に暗から明に移る世界を目の当たりにする時、
人は無から有の生ずることの感覚記憶を“再生する”。
日出日没のサイクルは自然に巡るが、意識の夜明けは、放っておけば勝手にそうなると言うものではない。
世界そのものは確かに放っておいても自然に覚める。
と言うか、とっくのとうに覚め、更に深く覚め続けている。

只、その覚めた世界に「放っておいてもいつの間にか覚めるよね」の算段で居た者が存在している保証は何処にもない。
夜の内に吹き荒れた嵐で、沢山花が散る。
惜しまず還して、未練なく夜を超えるか、
無明に遊び、いつの間にやら共に散るか。
どちらでも自由なのが、物理次元の素晴らしさである。

自由の本道に、誘導なし。
(2021/3/1)