《俗なる光》
前回の最後に、明るさも、適材適所と申し上げた。
眼が冴える熱なき光とは、起床から日中にかけてをメインにして付き合うと、生活に馴染む方が多いだろう。
日昇と日没の光は、そのおおまかな開始と終了を知らせる目安となる。
と言っても、現代社会の生活では、残業、夜勤、勉強、趣味、娯楽etc、熱なき光の出番は人によって何時でも何処でも幾らでも出て来る。
お日様など大いなるものに主権を委ねることが出来ないので、それぞれの意志決定が必要となる。
こう言うかたちでも、人類は虚空から自立を促されているのだ。

聖なる光などと言う様に、光は何かと聖性と結び付けられて来た。
暗闇の中にともる灯りは安心をもたらし、人はそれを聖なる輝きと感じたりする。
このこと自体は別に誤りではない。
万物に聖性は宿るからである。
全体一つの中で、光に聖性があってもおかしくはない。

おかしくなるのは、「光“は”聖のみ善のみ」等、限定した場合。
何故光が、聖を代表するものみたいになるのか。
ずっと不思議だったのだが、熱なき光の広がりとそれによる影響を観察していて、この明るさが聖性に結びつかないものであることに気づいた。
むしろ自在に広がり日々に溶け込み、好き勝手に騒ぐ元になり、何と言うかこう、逆。
そこまで気づいて、ふと
「……あ!俗なる光か!!」
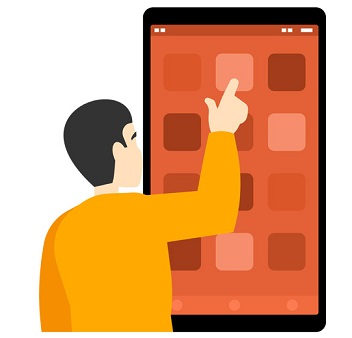
と、ハッとなった。
そして心底から納得し、満足した。
聖なる光があるのなら、
じゃない方もあるはずだ。

なのに偏った状態でしか注目されていないことが、どうにも腑に落ちなかったのだ。
実際、現代不覚社会は俗なる光で溢れ返っている。
光自体には良いも悪いもないし、聖俗どちらかだけに限られている訳でもない。
そのことに、俗なる光は改めて気づかせてくれたのだ。

限定不要の時代。
(2025/2/3)
