《あかり照らせば》
昨年から、人間の意識と空間との相互作用について注目し、折に触れて観察し続けている。
場所を増やしたい時に高層化したり、
火災や地震に強い素材に換えて建て直したり、
省エネになる仕組みを採用したり、
人々の求めに応じて、生活の場である住宅や、仕事を行う職場などの空間は変化を続けている。
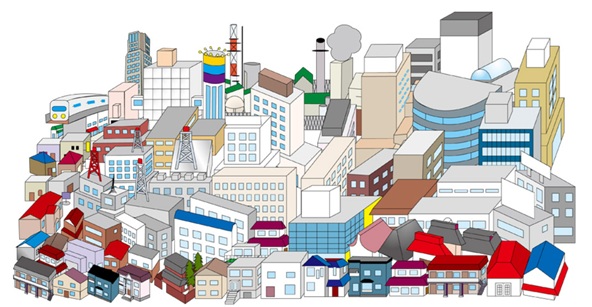
同時に、そうして生まれた空間が、中で過ごす人々の意識に変化をもたらしてもいる。
変化について知りたい時、今の今機能している生活や仕事の場に居るだけでは気づかないこともある。
そんな訳で気が向いた時に、現代ではもう作られない、江戸や明治、大正、昭和の初め位の建物を訪ね、そこへ静かに身を置いて過ごすことにしている。
このところは前もって知識を入れることなく行って、空間から伝わるものをそのまま味わってみている。

そうしてから解説を読み、その上で再び静かに空間を味わう。
体験、そして情報を得て知識を増やしてからの体験。
作られた経緯や、建築上の特色を知った上で改めてその場に身を置くと、どんな変化が起きるのか。
それを確認することも、とても面白い。

まず最初に居ることと味わうことをしているからか、「前時代の化石」ではなく生きた存在としての空間の力を感じる。
そうしている時に突然、驚く様な気づきが起きたりする。
例えば、人が過ごす空間に欠かすことの出来ないもので、「広さ」や「温度」「湿度」と並んで重要なのが「明るさ」。
現代の建物と前時代の建物を比較する時、明るさの度合いや、灯りの色や質が著しい変化を遂げていることに気づく。
昔の建物は何と言うか、暗がりが「しっとり」している。
陰影が風情に繋がる感じ。

そして陽が落ちると、灯りがあっても周囲の暗さは現代とは段違い。
本当に「とっぷり」と言う表現が相応しい。
こうした環境では、一個人にも人間全体にも「人の方でお天道様に合わせる他ない」と言う感覚が身につく。
それについて、古い時代の方が人間的だとか自然だとか、いい感じにまとめたくなる人も居るだろう。
今回申し上げたいのはそうした“昔は今より良かった話”みたいなものでは勿論ない。

人が自力で点せる灯りの力が小さく、お天道様に合わせる他ないと感じる時代。
それと同時に、暗黙の了解とか不文律とか呼ばれて、意識の暗がりに蔓延っていた自然ではないものも、何となく人々の間で
「それはそう言うものだから」
と片付けられ易かったのじゃないだろうか。
権力を持つ人が無理強いをする
なんてことも大多数の人にとっては「それはそう言うものだから」。
ここから展開して分かったことについては、次回に書かせて頂く。
興味深いのは、明るさが強度だけでなく、質においても変化したことである。

逃げ場なき、均一な照らし。
(2025/1/23)


